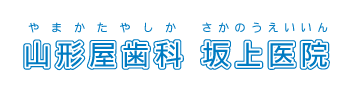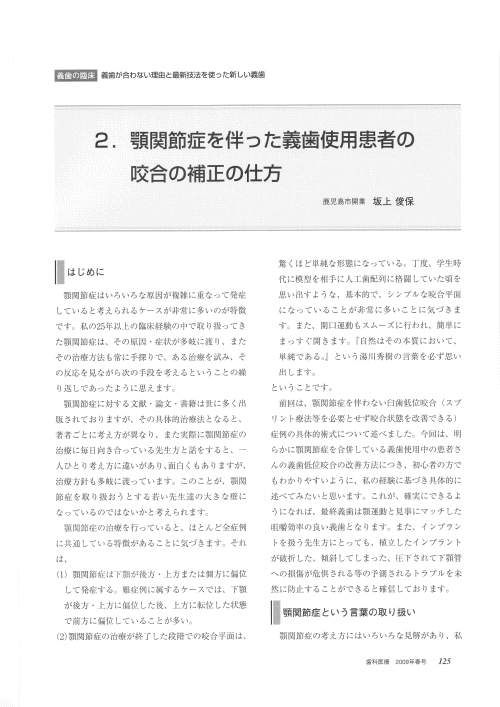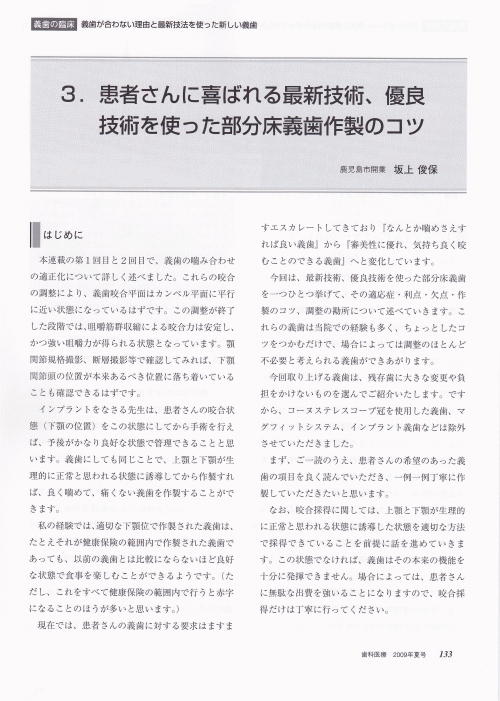論文発表
多くのインプラント治療のうまくゆかなかった患者さんにとって、再びインプラント治療を希望されるケースは、かなり少ないと考えられます。
インプラント不成功によって味わってきた、金銭的負担、苦痛や失望や今後の不安について考えると無理もない事だと思います。
|
では、下の写真を御覧下さい。
 |
このような口腔内の状態の患者さんが、欠損補綴を希望して、貴歯科医院を来院されたら、どのような治療計画をたてられますか?
こんな患者さんを見た時、一番最初に何をお考えになりますか?
『この患者さんの口は正常な開口運動・閉口運動ができるだろうか?』
と直ぐに疑うことができますか?
このような患者さんに、いきなりインプラントや義歯を作製して、
その後患者さんの口腔内で適切な機能を果たすことができると、
お考えになりますか?
|
欠損補綴においては、最終的に有床義歯が選択される事が非常に多い事になります。
しかし、不幸にして植立したインプラントを除去しなくてはならなくなり、インプラントと周囲の骨を一緒に摘出した場合に、歯槽は痩せてしまい、こういったケースに責任を持って、義歯を作製するためには、平素からそれなりの研鑽を積んでおかないとなかなか難しいと言わざるを得ません。
ご存知の通り、インプラントの禁忌症、疾患は非常に多く、主なものは、
心臓疾患、狭心症、心筋梗塞、不整脈など さらに広く循環器系疾患 糖尿病 膠原病など女性に多い免疫性疾患 慢性、急性期の肝炎、肝硬変
多くの血液性疾患:鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、骨髄性機能不全
(再生不良性貧血、赤血球無形成症など)、ポルフィリア、溶血性貧血
自己免疫性貧血
脳血管障害・脳梗塞 慢性腎疾患・人工透析患者 慢性腎疾患 内分泌性疾患
などが挙げられます。
高齢や生活習慣病のために
免疫力の低下した患者さんに安全に治療を行う準備が出来ていないのが実態です。
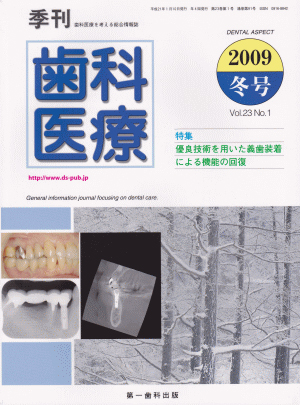
|
上の写真の症例においては、上顎歯列と下顎の歯槽頂までの距離がかなり接近しており、正常な形態の義歯もインプラントも作製不可能であるのは一目瞭然です。
さらに、このような患者さんには、しぱしば『ブラキシズム』があるためインプラント治療をこのままの状態で行った場合には、後から不都合が起こってくるケースも珍しくありません。
義歯にしても同じ事で、このような状態では、まともに食物を噛むことのできる義歯はとうてい作製できないでしょう。
このような症例に対して、どのように治療を行ってゆけば良いのか
有効な治療法につき、お若い歯科医師の先生方向けに執筆いたしました。
この内容を、
第一出版株式会社の依頼により
季刊『歯科医療』(第一歯科出版)
に1年に渡り、特集として論文投稿をさせて頂くことになりました。
|
1.義歯低位校合の診断と修正の勘所
―咀嚼効率の良い義歯の校合をめざして―
はじめに
近年のインプラント技術の発達には目をみはるものがある一方で、適応症や術式が適切でなかったとめに、インプラント除去を行わなくてはならないケースも後を絶たちません。
また、『手術』というものに対する恐怖心から、インプラントを希望せず、良質の義歯を求める患者さんが多いことも事実です。
義歯であれインプラントであれ、治療の際に細心の注意を払わなくてはならないのは、まず適切な咬合状態を構築することだと考えます。
この、咬合状態が的確に設定できれば、義歯の場合には最大較合力が増し、最終的に装着した義歯に十分に満足してもらえます。
(『はじめに』より抜粋)
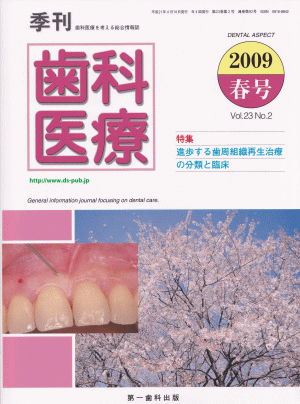
|
春号では、典型的な顎関節症を伴った症例についての診断法・および下顎の生理的に正常に位置への誘導法につき、具体例を挙げて詳しく解説しました。
この方法に対する十分な理解なくしては、顎関節症の治癒は望めません。
私の述べた方法は、下顎の誘導のひとつの方法に過ぎません。
他にも色々な方法が存在します。
確実に自分で治癒に導くことが出来る方法を身につける事が大切です。
|
2.顎関節症を伴った義歯使用患者の咬合の補正の仕方
顎関節症はいろいろな原因が複雑に重なって発症していると考えられるケースが非常に多いのが特徴です。
私の25年以上の臨床経験の中で取り扱ってきた顎関節症は、その原因・症状が多岐に渡り、またその治療方法も常に手探りで、ある治療を試み、その反応を見ながら次の手段を考えるということの繰り返しであったように思えます。
顎関節症に対する文献・論文・書籍は世に多く出版されておりますが、その具体的治療法となると、著者ごとに考え方が異なり、また実際に顎関節症の治療に毎日向き合っている先生方と話をすると、一人ひとり考え方に違いがあり、面白くもありますが、治療方針も多岐に渡っています。
このことが、顎関節症を取り扱おうとする若い先生達の大きな壁になっているのではないかと考えられます。
(『はじめに』より抜粋)
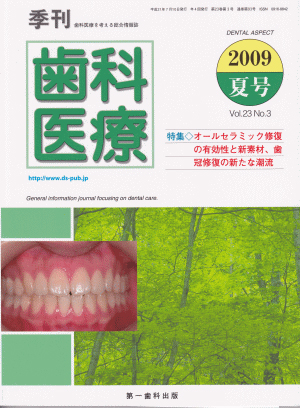
|
夏号では、主に部分床義歯を取り上げ、その種類・適応症・義歯作製における臨床上の勘所につき解説致しました。
患者さんに喜んで頂ける義歯として
・スマイルデンチャー
・コンタクトデンチャー
・スマイルデンチャーC+
・スマートデンチャー
・金属床義歯
を取り上げました。
義歯を作製する上で最も基本となる印象採得に関しては、
『アルジネート積層印象法』
『超精密印象法』
に関して詳述し、皆さんの日常の臨床に直ぐに応用出来る内容となっています。
|
3.患者さんに喜ばれる最新技術・優良技術を使った部分床義歯作製のコツ
本連載の第1回目と2回目で、義歯の噛み合わせの適正化について詳しく述べました。
これらの咬合の調整により、義歯咬合平面はカンペル平面に平行に近い状態になっているはずです。
この調整が終了した段階では、咀嚼筋群収縮による咬合力は安定し、かつ強い咀嚼力が得られる状態となっています。
顎関節規格撮影、断層撮影等で確認してみれば、下顎関節頭の位置が本来あるべき位置に落ち着いていることも確認できるはずです。
インプラントをなさる先生は、患者さんの咬合状態(下顎の位置)をこの状態にしてから手術を行えば、予後がかなり良好な状態で管理できることと思います。
義歯にしても同じことで、上顎と下顎が生理的に正常と思われる状態に誘導してから作製すれば、良く噛めて、痛くない義歯を作製することができます。
私の経験では、適切な下顎位で作製された義歯は、たとえそれが健康保険の範囲内で作製された義歯であっても、以前の義歯とは比較にならないほど良好な状態で食事を楽しむことができるようです。
現在では、患者さんの義歯に対する要求はますますエスカレートしてきており『なんとか噛めさえすれば良い義歯』から『審美性に優れ、気持ち良く咬むことのできる義歯』へと変化しています。
今回は、最新技術、優良技術を使った部分床義歯を一つひとつ挙げて、その適応症・利点・欠点・作製のコツ、調整の勘所について述べていきます。
これらの義歯は当院での経験も多く、ちょっとしたコツをつかむだけで、場合によっては調整のほとんど不必要と考えられる義歯ができあがります。
(『はじめに』より抜粋)
今後、良い義歯を作製する為に必要な噛み合わせに対する知識や、下顎の誘導法、新しい技術・優良技術を使った義歯を作製してゆく上で必要となってくる知識、技術、臨床での勘所につき御紹介してゆく予定にしております。
興味のある先生には是非御一読頂ければ幸いです。
|